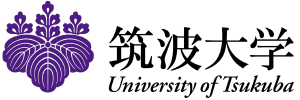仮想(バーチャル)空間と現実空間の連続性を探りたい
雨宮 怜
AMEMIYA Rei
筑波大学 体育系

深刻化する孤独の解消目指して仮想空間に着目
現代を生きる私たちは日々さまざまな科学技術の恩恵を受けて暮らしていますが、その一方で人と人との繋がりは希薄化あるいは悪化が進み、そこから生まれる孤独や疎遠が心身の健康に悪影響を及ぼすことは広く知られているところです。
今後この流れは、災害や感染症の拡大、さらには国家間の争いといった緊急時も含め、ますます深刻化すると予測されており、その流れを食い止めるものとして台頭してきたのが、人が直接会わなくても交流できる場、インターネット上の仮想空間=メタバースです。
ところが、メタバースやVRなどのバーチャル空間は、誕生当初は爆発的な注目を集めたものの、じきにやや失速気味に。その活用も下火になっている現状です。
場所というものは本来「その場所で何をするか」という目的とセットで成立するものであり、そこが噛み合ってはじめて、その場所の価値や効果が高まります。
野球場で野球を、サッカー場でサッカーをするように、メタバースで現実空間のように他者との交流や関係性の構築が可能であることを示すことができれば、懸念される未来の社会像に貢献できる知見を世界に提案できる。そう考えた本プログラムでは、仮想空間と現実空間との連続性を探っています。

KIMULAND上の活動の様子
ペア活動後に縮まった17cmの正体を明らかに
私の専門は体育心理学です。通常、アスリートのメンタルトレーニングやチームワーク向上を支援する心理プログラムの実践や効果測定を行っています。
本研究は「現実空間と仮想空間は地続きの空間なのか、それともパラレルワールドのように、全く別の世界として見た方が良いのか?」という私の素朴な疑問から始まりました。
仮想空間を活用した研究は多々ありますが、現実空間との連続性や人と人との関係に及ぼす影響について検討したものは先行例がなく、そこに挑みます。
今回の実験では互いに面識のない大学生たちを二つのグループに分け、一つのグループにはメタバース上でサッカーなどのペア活動を、比較対照群であるもう一つのグループにはペアであることは伝えつつ、メタバース上で個人活動をしてもらいました。
活動前後に両グループとも心理検査を行い、さらに現実での対人距離を測るため、二人が向き合って座る椅子と椅子の間の距離を測るストップディスタンス法を用いたところ、比較対照群では対人距離が平均0.4cmしか縮まらなかったにもかかわらず、ペア活動を行ったグループではおよそ17cm距離が近づくという結果を得ることができました。
こうした量的研究に加えて、今後は研究対象者たちの体験に迫る質的な研究も取り入れ、混合研究法ならではの検討を重ねていく点も、本研究の独自性に挙げられます。
「メタバース上での活動が現実空間の心理・身体的対人距離に及ぼす影響」という発表が、日本心理学会第87回大会の優秀発表賞をいただきました(https://psych.or.jp/prize/conf/)。
今後もペア活動後に縮まった17cmにはどういう意味が込められているのか、現実空間と仮想空間の関係性について解像度を高めていきたいと考えています。

対人距離を測定するためのStop-distance法を実施する様子
社会実装を実現する多様なチーム編成に期待
本プロジェクトは体育心理学が専門の私と、心の健康の専門家である臨床心理学の菅原大地先生、教育現場をフィールドとする教育心理学の上野雄己先生という、心理学を共通言語とする多様な専門領域の研究者たちの分野融合で進めています。
将来的に仮想空間と現実空間の連続性を活用できるようになれば、企業や学校、スポーツでのチームビルディングやソーシャルスキルトレーニング、あるいは身体に不自由を抱える人たちの社会参加、冒頭に触れた緊急時の交流など、幅広い応用が可能になります。
それを実現するためにも、この先はさらに広がりのあるチーム編成が必要不可欠。メタバース関連の企業や情報工学の方々とぜひとも繋がりたいという思いとともに、未来に向けたこの試みを人文科学の視点から検証する哲学、経営、社会学などの人文系の方々との連携も、心より楽しみにしております。